からだに対する誤った意識と正しい意識
良い姿勢を意識するために「胸を張れ」とよくいわれます。そうすると、筋肉を緊張させて肩甲骨を後方へと引き、胸の筋肉が突っ張った状態を作り出そうとします。緊張させた肩甲骨間の筋肉は疲労し、突っ張った胸の筋肉は、血管が圧迫されて血行不良となります。
肩甲骨間の筋肉を縮めて胸を伸ばすのではなく、胸の側も肩甲骨間も伸びて広がるように意識するとそのようにはなりません。
「顎を引く」というのも、また良い姿勢を意識するためによくいわれます。そのように意識すると首の前側の筋肉を緊張させて顎を胸の方へと引きつけようとします。そのためにやはり首の前側の筋肉は疲労し、後側の筋肉は引き伸ばされて血行不良となります。
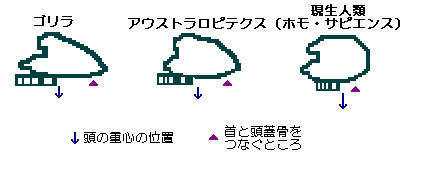
背骨を持つ動物は、水平な背骨の前方に頭のある四足動物から、類人猿・猿人・原人・旧人・現生人類へと進化するにつれて、背骨の方向は水平から垂直へ変わってゆき、頭の重心は首の骨と頭蓋骨との関節に近づいて、現生人類では頭の重心は首の骨と頭蓋骨をつなぐところより少し前にあります。それにより脳が大きくなり重たくなっても安定性を損なわない構造となったために脳は大きくなり、今日の文明を築くことができました。そうした構造のために頭を支えるのに要する筋肉は小さくてもすむようになりましたけれども、これに過度の負担がかかると疲労を起こしやすくなります。首より下が正しい状態にあれば、頭の重みは頭蓋骨と首の一番上の骨との関節を支点として顎の側が下がり、靭帯や筋膜・筋肉がその張力により頭を首の上で支える状態となります。
顎が上がった状態を解消するためには、首から下を正しい状態にして後頭部が上へと引き上げられるようにと意識します。
以上のような人体の骨格構造に基づいた姿勢等に関する助言を行います。
※ 参考文献 フィオレンツォ=ファッキーニ著 片山一道訳「人類の起源」 同朋社出版